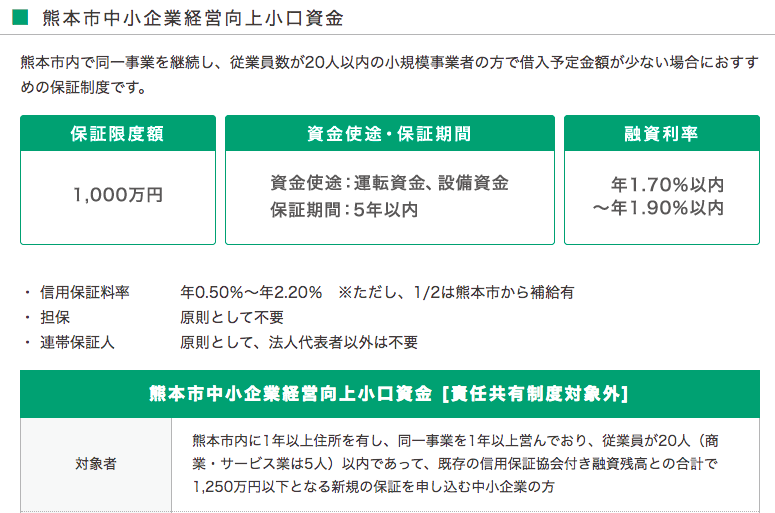当サイトは事業用の資金調達・資金繰りノウハウを提供するサイトですが、訪問者の中には単純に日々の生活に困って情報収集し、当サイトに到達される方もいらっしゃいます。
しかしながら、日本政策金融公庫では事業用の融資が主で、借金返済や生活の為の融資は日本政策金融公庫ではできません。
借金でお悩みの方は、まずは融資の前に「過払い金」がないかを調べる事からスタートしましょう。
過払い金がない方でも、借金の整理や生活の立て直しの為の行政手続きや融資制度は多々あります。
事業用ではない以上、日本政策金融公庫や信用保証協会付融資を受けることはできませんが、諦めずに生活の立て直しのために参考にして頂ければ幸いです。
【目次(もくじ)】
- 1.個人再生
- 2.疾病手当金
- 3.失業保険
- 4.生活保護
- 5.障害年金
- 6.求職者支援制度
- 7.生活福祉資金貸付
- 8.臨時特例つなぎ資金
- 9.住宅確保給付金
- 10.国民年金保険料の免除・猶予
- 11.国税の猶予
1.個人再生
個人再生とは借金が返済できないときに行う債務整理の1つで、裁判所に申し出て借金の総額を減らしてもらう手続きのことをいいます。
裁判所に再生計画の提出を行い、これが認められると債務が1/5に減額され、3年間で返済するのが一般的です。3年での返済が困難な場合は、5年間の返済期間が認められることもあります。
個人再生の最大の特徴は、自己破産とは異なって、決められた条件を満たせば自宅を売却しなくてもすむことです。このためマイホームを手放さずに債務整理ができます。(マイホームを手放さずに済む方法にリースバックという方法もあります。)
また家族が保証人でない限り、その家族に迷惑がかかることはありませんし、家族がローンを組む場合にも個人再生が理由で利用できないというここともありません。
仮に過払い金はなくとも、借金が減額される可能性がありますので個人再生も検討してみてください。
【参考コンテンツ】
2.疾病手当金
疾病手当金とは病気やケガで勤めている会社を休んだときに、会社から十分な給与が受けらることのできない場合に支給となる健康保険の制度です。この手当を受けるためには、次の4つの条件を満たすことが必要です。
1つ目は、業務以外の理由による病気やケガで、仕事を休んでいること。
2つ目は、病気やケガで仕事ができないこと。このときの判定基準は医師の意見と、その人の仕事内容によって判断されます。
3つ目は、病気やケガのために仕事を休んだ日から3日間連続したあと、4日目以降も仕事に就けないこと。この場合は最初の3日間は手当の支給対象になりません。4日目の休んだ日に対してのみ支給されます。
4つ目は、休業した日に対して事業主から給与が支払われていないことです。
仕事でのケガなどには労災保険が支給されますが、仕事以外での病気やケガは労災対象にはならないため、被保険者とその家族が生活に困らないように設けられた制度です。
3.失業保険
失業保険はこれまで働いていた職場を退職するなどして職がなくなったときに、次の仕事が見つかるまでの期間に対して、お金が支払われる保険制度です。
失業期間中でも生活費に困らないようにお金を支給して、この期間に職探しに専念できるようにするための制度です。
ですから失業保険を受け取るためには、その人に再就職をしようという意志があり、就職活動に取り組んでいる必要があります。
独立して起業するための退職や、結婚して専業主婦になる人などに対しては、失業保険は給付されません。失業したらまず、ハローワークに求職の申し込みをしましょう。
これに加え、退職した日より前の2年間に雇用保険に入っている期間が、12か月以上であることも支給条件となります。
4.生活保護
生活保護とは、失業などで収入がなくなり生活費が工面できない人に対して、最低限必要な生活費を支給して、健康で文化的に暮らせるように支援するとともに、金銭的に自立できるようにサポートする国の支援制度です。
生活保護法に基づくもので、厚生労働大臣が定めた最低生活費より低い収入の人に支給されます。
生活保護には目的別に8種類の扶助があります。
第1は、生活扶助。食費や衣服代、光熱費など生活に必要不可欠な費用です。
第2は住宅扶助で、決められた範囲内で家賃のための費用です。
第3は教育扶助で、子どもの義務教育に必要な費用です。
第4は医療扶助で、病気やケガなどを治すために必要な医療費が無料となります。
第5は介護扶助で、介護を受けるための費用を扶助します。
第6は出産扶助で、出産に必要な費用が、支給されます。
第7は生業扶助で、就職するための技能の習得費用です。
第8は葬祭扶助で、お葬式のための費用です。
生活保護を受けることは恥ずかしいことではありません。生活に困った場合には一人で思い詰めずに、行政へいち早く相談してください。
5.障害年金
障害年金とは年金に加入している人を対象に、病気やケガで日常生活に支障をきたす障害がある人に支給されるお金です。
国民年金に加入している人には障害基礎年金が、厚生年金に加入している人には障害基礎年金に障害厚生年金を上乗せして支払われます。この年金は法令によって決められた障害等級表によって、1級と2級に分かれています。
障害年金をもらうためには、初診日に年金に加入していること、重い障害があること、初診日の前日に保険料の未納がないことなどの条件を満たしている必要があります。
これらの条件を満たしているかどうかを判断するために、初診日を証明する書類や、医師の診断書、障害の状態を説明する病歴・就労状況等申立書、戸籍謄本、住民票など、さまざまな書類をそろえて年金の請求を行わなければいけません。
【参考コンテンツ】
6.求職者支援制度
求職者支援制度とは就職を希望する人のために、無料や低価格で職業訓練を実施したり、ハローワークなどがその人に応じた就職サポートを実施したりすることで、就職を可能にするための制度です。
職業訓練を受けるための受講給付金が支給など、充実したサービスが提供されています。
支援制度が受けるためには、次の4つの条件を満たす必要があります。
第1は、ハローワークを通じた求職活動をしていること。
第2は、失業保険を受給していないこと。
第3は、働く意志があること。
第4は、ハローワークから職業訓練を受けるための支援が必要であると認められたことです。
これまで自営業を営んでいた人が廃業した場合も、支援制度が受けられるので積極的に活用したい制度です。
7.生活福祉資金貸付
生活福祉資金貸付とは、収入の少ない人やお年寄り、障害のある人が就学や就職のための技術習得、介護サービスなどを受けるために必要なお金を貸し付ける制度です。
各都道府県にある社会福祉協議会を行っており、都道府県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって受け付けています。世帯の経済状況などに合わせた貸付を行うとともに、民生委員が相談に応じています。
貸付資金の種類は福祉費や教育支援資金、そして不動産担保型生活資金に総合支援資金、さらに緊急小口資金があります。
2016年度から生活困窮者自立支援法が施行され、この貸付制度の内容にも変更されました。収入が低い世帯の人が就職などによって自立できることを目的とし、総合支援資金と緊急小口資金の貸付は就職が内定している人に対して行われないようになりました。
また自立相談支援機関を利用することが貸付の条件となっています。
8.臨時特例つなぎ資金
臨時特例つなぎ資金とは、離職して生活に困っている人のための貸付制度です。
この制度を利用できる人は、離職して住むところを失った人です。そして次の2つの条件を満たしている必要があります。
第1は、失業給付金や住宅手当、職業訓練受講給付金、住宅支援給付金、生活保護など離職者を支援するため公的給付金や、就職安定資金融資金融などの公的な貸付制度の申請が受理されている人で、給付金や貸付金を受け取るまでの期間の生活に困っている人。
第2は、本人名義の金融機関の口座があることです。
貸付金は10万円までで、貸付金額はその人の状況に合わせて決まります。連帯保証人はいりませんし、利子もつきません。
市区町村の社会福祉協議会が受付窓口になっています。
9.住宅確保給付金
住宅確保給付金とは失業や自営業を廃業するなどして収入の道が途絶え、住むところを失った人や失う恐れがある人を対象に、住むところを確保するために家賃分のお金を給付する制度のことをいいます。
給付金の支給対象となる人は、現在職がないけれど、就職をして自立が見込める人です。
このほかにも決められた条件を満たす必要があります。
離職日から2年以内で、65歳未満であること、離職時点で家族の収入を得るうえで中心となっていたこと。
ハローワークに求職の申込みをし、長期就職のために努力すること。
国や地方自治体から同様の給付金をもらっていないこと。
家族に暴力団員がいないことも条件です。
さらに一定以上の収入や資産がある場合も、給付対象となりません。
対象となる収入額や資産額は、地方自治体によって異なります。
この制度の相談窓口は、地方自治体によって異なりますが、お住いの都道府県のホームページなどで確認できます。
10.国民年金保険料の免除・猶予
収入が著しく低下して国民年金保険が納付できなくなったときに、保険料の免除や納付猶予の手続きを行いましょう。
この手続きをしないまま保険料の支払いを滞納すると、保険料が不払いとなって将来年金を受け取る額が少なくなるなどのデメリットがあります。
しかしこれらの手続きを行うと、免除や猶予となった期間は不払いとはなりませんから、万が一この期間にケガや病気で障害を負ったり、死亡したりといったことがあっても、障害年金や遺族年金が支給されます。
保険料の免除では世帯所得が一定額以下になった場合や、失業して所得が0円になった場合など支払いが困難と認められた場合に、納付が免除され、その期間は年金が支払われたものとみなされます。
免除には全額、保険料の3/4、半額、1/4の4つに分かれており、審査によって決められます。
納付猶予の場合は一定期間の支払いが猶予されますが、この期間は年金の支給額が反映されません。
11.国税の猶予
税金を支払うのは国民の義務ですが、経済的な事情で支払うことが難しくなる場合もあります。
だからといって税金の滞納を続けていると、財産を差し押さえられることがあります。このような事態に陥らないようにするための手続きが、換価の猶予と納付の猶予です。
換価の猶予とは、財産を差し押さえてこれをお金に変えて税金の納付に当てる処分を待ってくれる制度で、猶予期間は延滞税が免除されます。
ただし税金を納めようとする前向きな意志があり、他の国税の滞納がないことなどが条件となっており、原則として担保が必要です。
納付の猶予とは、税金の支払いを待ってくれる制度です。災害や盗難、事業の廃業などやむを得ない事情の場合に限られます。
支払期日までに税金が納められない場合は、所轄の税務署に相談しましょう。